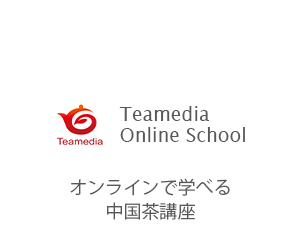茶本主义:中国人的茶感觉系统演变史
中国人贪念茶叶的香气与滋味,“蒸青”即以热气煮蒸方式将鲜茶所含各种香与味的成分保留下来,以供享受;鲁成银说:“炒青”技术的价值在于,高温急炒,一则将那些低沸点的芳香物,比如青草气(日本茶里淡淡的“海苔味”即此种物质)给挥发掉了;同时,炒的过程本身,又重新进行了物质转化与聚集--香气与滋味,由此更上台阶。科学测定,茶叶鲜叶所含香气成分种类不多,约50种;而经过制茶程序之后,绿茶香气成分可达110种--绿茶工艺,其实主要也就是各种手法的“炒”而已;而红茶则可达325种。茶叶香气成分的这种跃进,其核心性技术的突破,在现代的科学家如鲁成银看来,关键当然是“炒青”。
本篇文章来源于第一茶叶网 原文链接:http://news.t0001.com/2010/0601/article_109158.html
炒青緑茶と蒸青緑茶のことについて書いてあります。
日本緑茶の蒸製仕上げだと、沸点の低い芳香物質である青っぽさ(海苔味と言ってます)が残るのに対し、高温での炒青をすると香りが高まると言っています。
科学的に測定すると、生茶葉の中の芳香物質は50種類ぐらいしかないのだそうですが、製茶の過程を経ると緑茶の場合で110種類に達し、その主要な要因は炒青にあるとしています。ちなみに紅茶は325種に上るそうです。
なぜ、日本では蒸青が残り、中国では炒青技術が用いられるようになったのか、ということについては、はっきりしたことは分からないのですが、中国人の感覚の変化が挙げられるといいます。
唐宋代の貢茶は、規定の香りと味であることが求められたため、新しいことを追求する要素はありませんでした。しかし、それが明代に入ってから自由になったことで製茶法にも変化が現れました。
炒青技術が普遍的に使われるようになったことで、緑茶からまず黄茶、黒茶などの湿熱酸化を用いるお茶が生まれ、そのあとに酵素による酸化を用いた青茶や紅茶が出来ていったと考えられています。
宋代までの規律を守り続けた日本と、そこから自由になって色々な製法を考えた中国。
どうもそこが日本茶と中国茶の分岐点になったようです。